横山で一輪のみに終わったヤマシャクにもう一度会いたくシルバー隊の案内を兼ねて行者還へと車を走らす。
奈良のヘソ黒滝道の駅で大阪組シルバー隊と合流し登山口のあるトンネル西口に8時30分に到着。
京阪くずはを出て約3時間30分、105kmのドライブである。
昨年同時期にも訪れており、ヤマシャクとシャクナゲの大歓迎を受けたことが忘れられず
準備をしながら期待感が徐々に高まってくる・・・咲いているかな! 世界遺産の看板を見ながら登山道へ入ってゆく。
今日のコースはトンネル西口から行者還ピストンのベーシック!
|
 |
 |
 |
| 西口駐車場・・・さすがに世界遺産 |
世界遺産の看板が目立つ |
弥山・行者還登山口 |
|
登山口の小橋を渡ると左側の斜面に行者還への取り付きがあり、シャクナゲの群生する急斜面を
奥駆道、しなの木出合へと登って行く。 (直進すると弥山、八経へのルートである)
50分程あえぎながら登ると急斜面が終わり、奥駆道出合に着く。
ここで一息入れて新緑の美しい行者還への世界遺産奥駆道をゆっくりと歩きはじめる。
|
 |
 |
 |
| 行者還への取り付き |
急斜面を登る |
奥駆しなの木出合 |
|
行者還への奥駆道はアップダウンも少なく、左手に弥山、八経、鋭い三角錘の鉄山、
進行右奥に大峰の主、大普賢様を見ながらの快適トレッキングが続く。
残念ながら名物のシロヤシオはまだ蕾の状態であるが、ブナ、カエデの新緑が目にやさしく最高!!
平均年齢六十数歳のシルバー隊の歩みも順調で立ち枯れとのコラボの何故か微笑ましい!
|
|
|
 |
 |
| 八経、弥山 |
鉄山 |
|
 |
| 大峰の主大普賢 |
|
大峰奥駆道の標柱より苔むした小山を巻く道になると足元にヒメレンゲやハルリンドウが顔見せ始めてくる。
小山を巻き終わると白く大きな花が一輪・・・ヤマシャクである。 パチリと一枚撮り少し進むと群生地があり満開!
|
 |
 |
 |
| 標柱より小山をトラバース気味に巻いて行く |
ツルキンバイもチラホラ |
|
|
|
昨年よりもたくさんの花を付けているようであり、何度もパチリとシャッターを押して遥々遠征してきた感激に浸る。
昭和の企業戦士であったシルバー隊の皆さんも貴婦人に会い久しぶりに気持が昂っている様子。
|
|
|
目と心が癒された後、バイケソウともう少し開花が先であるクサタチバナの群生地を抜けると
前方上部に行者還の頂を見上げるようになり大川口からの関電道と合流すると行者還の宿へと着く。
|
 |
 |
 |
| バイケソウの海を抜ける |
名花クサタチバナはまだ蕾 |
前方の行者還へ稜線を行く |
 |
 |
 |
| バイケソウと大普賢 |
行者還の岩峰 |
きれいな行者還の宿 |
|
小屋の後には行者さんが登るのを断念し、名前の由来にもなっている岩峰が高くそびえる。
小屋でシルバー隊の休憩タイムを取り、行動食を頬張り15分程体力回復の時間に充てるとシりバー隊も元気100倍!
さあ! 頂へ 行者還を右から巻くように奥賭道を進み崩壊地に付けられた梯子を登って行く。
|
 |
 |
 |
| 奥駆道は行者還を右側から巻く |
長い木製の梯子を登る |
ガンバレ! シルバー隊トヨ爺 |
|
七曜岳との分岐を左に折れて奥駆道よりはずれている頂へのルートへ進み少し登ると行者還山頂へと着く。
山頂は360度の展望とはいかないがアカやピンクのシャクナゲに囲まれた別天地である。
|
 |
 |
 |
| 七曜岳分岐 |
山頂へ向かう道 |
山頂はシャクナゲの群生地 |
|
シャクナゲを観賞した後、樹林の間より見える弥山、稲村、大普賢を楽しみながら昼食タイムへ。
単独で登って来られた男性の方と大峰の山を語らい1時間程のんびりと過ごして七曜岳分岐より小屋へと戻る。
|
 |
 |
| 八経、弥生、手前に未踏の鉄山 |
稲村ヶ岳と左に未踏のバリゴヤの頭 |
|
|
|
小屋からは元来た奥駆道をしなの木出合いまで年金の話をしながらブラリ、ブラリと戻り
次回は大普賢様へ案内することを約束してトンネル西口に下山し、行者還ヤマシャクの旅を終える。
|
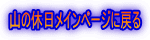 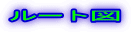 |


![]()