小屋に戻ると20名の団体さんと100名山を目指す先程のご夫婦がおられ夕食のカレーライスをいっしょにワイワイガヤガヤと食べる。
管理人さん自慢のカレーライスは美味しくみなさん元気にお代わりの連続・・・頼もしいかぎりで明日の登頂は約束されたようなものです。
夕食後は小屋の管理人さんが山の話をして下さり、この小屋、この山、あの花そして鳳凰三山の逸話などを訊き、
次回の為にオベリスクの登頂ルートもしっかりと頭に入れる・・・そしてお休み!
夜中に小屋がつぶれるのではないかと思うほどのはげしい雨とカミナリで目が覚め、明日は下山だなと再び寝袋に入り瞼を閉じる。
翌日朝5時に起きると昨夜の雨がうそのように止んでおり、団体さんの姿もすでになく、
4時に出発されたとの事で朝食を食べたのは我々二人とご夫婦の4人のみ。
いつものように支度に手間取りごちゃごちゃしていると段取りのよいご夫婦の方が出発され、さらに40分程遅れて小屋を出る
昨日管理人さんが話してくれた絶滅危惧種のクモイコザクラが小屋前に保護育成されておりパチリとカメラに収める。
|
 |
 |
| 朝の鳳凰小屋 |
絶滅危惧種のクモイコザクラ |
|
今日は稜線へのショートカットコースを選び小屋前の谷を渡り梯子に取り付いて樹林帯に入って行く
このコースはまだあまり人が歩いていないのか登山道に雪がしっかり残っており、クッションをきかせてけっこう楽に登ってゆける。
シラビソの中を30分程登り続けると三山縦走路に飛び出し、オベリスクが天を衝く姿に再びお目にかかる。
|
 |
 |
 |
| 小屋前の谷を渡る |
雪の残る登山道 |
シラビソの間よりオベリスクが! |
|
 |
 |
| 飛び出した砂礫の稜線 |
今日もオベリスクが天を突く |
|
快晴とまではいかないが雨の降る気配はなく、今日一つ目のピーク観音岳に向けて気持ちのよい稜線歩きのスタートを切る
砂礫地帯から岩道に入りどんどん標高を上げてゆくとやがて岩の塊にようなピーク観音岳に到着し、ザックをおろして岩に立つ。
白峰三山は雲に隠れてその全貌を見ることができないが、振り返って眺める地蔵のオベリスクがひときは鋭い。
|
 |
 |
| 観音岳への稜線 |
鳳凰山観音岳 |
|
 |
| 観音岳より地蔵を振り返る |
|
観音岳から薬師ヶ岳に向けては風化した花崗岩と砂礫の道がおだやかなに続き、快適な稜線歩きとなる
キバナシャクナゲが稜線沿いにずーっと咲き乱れ、薬師ヶ岳手前を歩く団体さんのリズムもなぜか楽しそうに届いてきそう。
相棒のミーとマン氏も奥様への画像プレゼントにするのか珍しく何度もキバナシャクナゲをカメラに収めている。
快晴であれば白峰三山を右に、八ヶ岳を左に、後ろに仙丈と甲斐駒を従え大三角に向うのであろうと創造するだけで楽しい。
|
 |
 |
| 観音岳から薬師への稜線 |
砂礫の道がなんとも優しい |
|
|
|
風化した花崗岩と砂礫、そしてキバナシャクナゲを楽しみながら穏やかな稜線山歩を楽しみ三山最後のピーク薬師岳に到着。
ここで鳳凰三山の稜線とお別れになるので名残りを惜しむようにコーヒータイムを取りのんびりと山の休日を楽しむ。 |
 |
 |
 |
| 薬師岳 |
薬師より観音岳を振り返る |
カーボイミーとマン氏と雨にならずに乾杯! |
|
薬師から青木鉱泉への中道は相当キツイコースのようで鳳凰小屋の管理人さん曰く、北アルプスの笠新道に匹敵するとのこと!
昨年より愛用の幅広登山靴の紐を締め直し、ザックの腰ベルトを調整していざ下山!
山頂から大きな岩の間を抜けて行くとすぐに樹林帯に入り、残雪で埋まる登山道をかかとで捉えて下る。
樹林の間より一時だけ薬師の山頂を望むことができるが以後全く展望なしとなる。 |
 |
 |
 |
| 薬師岳山頂付近の大岩帯 |
山頂直下樹林帯は残雪豊富 |
今下って来た薬師岳 |
|
薬師岳より黙々と30分程下り続けると御座石となずけられた大石に着く、この辺りから登山道にはガスが湧き出して
退屈な下りにサラに輪をかけてくれる。交わす言葉が次第になくなりただひたすらの下りになりおっちゃんの言葉がずしっと響く
登山道脇に咲くギンリョウソ、マイズルソウ、バイカオウレンが慰めてくれるのみ。
|
|
|
|
|
さらに下り続けて林道上部の出会いを通過し、さらにさらに下って下り続けること2時間20分林道にようやく到着して一息入れる。
ここから薬師岳に登る人がいるのかなあとあらためて長い退屈な下りに変な感心をする。
そして林道をゆっくりと歩きドンドコ沢を渡って青木鉱泉に戻る。
|
 |
 |
 |
| 林道出合い |
青木鉱泉まで長い林道歩き |
ドンドコ沢を渡る |
|
ちと高いなと思いながらも話の話題に1000円を払い鉱泉に入る。
観光ツアーの団体さんとバッティングしゆっくりはできなかったものの汗を流しさっぱりとして帰路に。
今回の山旅は豊富な天然水の滝を全て見ることが出来た事、岩の芸術であるオベリスクに触れることができた事
絶滅危惧種のクモイコザクラを見れた事、そしてなにより行き帰りの950キロを運転出来たことが
夏の遠征に向けての自信になったのが大きい。
|
 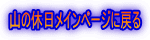 |

